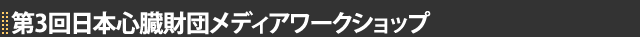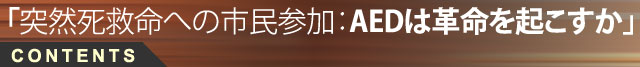
 |
 |
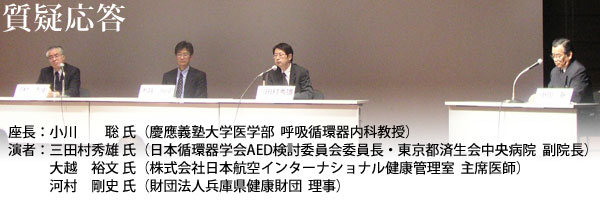 右から:小川聡氏(座長)、三田村秀雄氏、大越裕文氏、河村剛史氏
右から:小川聡氏(座長)、三田村秀雄氏、大越裕文氏、河村剛史氏
講演者の発言内容は、本ワークショップ開催当時(2004年6月23日)のまま記載しております。このため、記事では、AEDは基本的に医療従事者のみ使用可能であることを前提としておりますが、その後、7月1日に厚生労働省から通達が出され、医療従事者以外の一般市民にも使用が認められています。
AEDが認可され、普及するために必要なこと
小川氏:まず、自動体外式除細動器(AED)の行政上の認可について解説をお願いします。
大越氏:現在、厚生労働省では非医療職におけるAED使用のあり方を検討中で、近日中には回答が出ると思われます。使用の条件としては、
(1)現場に医師がいないこと
(2)意識、呼吸がないこと
(3)義務ではないが講習を受けていること
(4)薬事法による認可
になると思います。
会場より:AEDの普及を進めるにあたって、具体的には、国や自治体および医師会などはどのようにされたらよいとお考えですか?
三田村氏:一つは、心停止の発生率が高い公共の場所に、地方自治体や国が、主導的に配備をすすめるということが望ましいと思います。また、どうやって使用するかに関しては、できるだけ簡単な内容で効果を見込めるものを教育に反映させることが必要だと思います。
河村氏:国が決定した方針をもとに、教育委員会などが率先して判断をすべきだと考えます。
大越氏:公共の場にAEDを設置することと、学会やメディアからの提言が必要です。日本循環器学会のほうで、配備すべき場所については提言されているので、これを参考にメディアなどが推奨してくれたらと思います。
一般市民がAEDを初めて使用するときのポイント
小川氏:一般の人がAEDを初めて使う際は、不安を感じると思いますが、仮に使用した場合に、誤作動などの問題はないのですか?
三田村氏:一般の人が使えることを目指したものなので、そういった誤作動などには十分な配慮がされています。将来的にAEDがもっと広まった場合の予測は難しいですが。
小川氏:AEDを使用した場合の安全性はどうですか?
三田村氏:電気ショックがかかる瞬間に機器に触った場合、感電するような感覚はあるかもしれませんが、命にかかわるような事故の報告はありません。
小川氏:実際の救命率はどの程度ですか?
三田村氏:統計では出ていませんが、少しずつ増えてはきているようです。
会場より:AEDが適切に使用されれば、一発で脈が正常な状態に戻りますか?
三田村氏:一発では脈が戻らない場合もあります。発作の原因や除細動を開始する早さによりますが、原因がはっきりと分かった場合で、除細動の開始が早ければ早いほど救命の確率は上がるということです。
会場より:日本航空では、実際に使用しているわけですが、成果はどのようなものですか?
大越氏:何例かに使用はしましたが、残念ながら今のところ救命できた例はありません。発作を起こした患者を早期に発見できなかったりさまざまです。なかには喘息の発作から心停止を起こされた患者さんもいましたが、その時は諸事情によりAEDを使用できませんでした。
AED配備の状況
会場より:アメリカでは、AEDが劇場や映画館といった場所にも配備されているのですか?
三田村氏:かなりの率で配備されていますが、アメリカの場合は盗難などの問題もあるため、目立たないところに置いてあるようです。
会場より:現在、日本には何台のAEDがありますか?
三田村氏:およそ4,000台といわれています。
河村氏:兵庫県では、今年、保健センター25ヵ所と県立のスポーツセンター18ヵ所の合計43ヵ所に設置します。
会場より:値段はどの位ですか?
三田村氏:アメリカでは、1,500ドルから3,000ドル程度です。日本では定価で60万から80万の間と聞いています。ただし、今後、一般解禁され普及する数などによっては、値段が下がる可能性もあります。
一般市民へのAED教育のポイント
小川氏:一般市民へのAEDの講習会は、どういった目的でされているのですか?
河村氏:一般の人にAEDの存在を知っていただくためです。発作がおきて倒れている人を見つけたときに、AEDを使用するという意識を持ってもらうために必要だと思います。
会場より:AEDの教育を学校で行う際のポイントはなんですか?
河村氏:学校の先生方の意識付け、教育の現場で行うことが大切だと思います。
会場より:一般の人が、倒れている人を見たときにそれが貧血なのか心室細動によるものかの見極めは難しいように思いますが、見極めるポイントはどこですか?
河村氏:倒れている人が呼吸をしておらず、脈もなければ心室細動です。AEDの使用に関して言えば、極論だと、脈がなく意識もないことが確認できれば、除細動で5分以内の死亡は防げるということです。
三田村氏:そういった見極めができるようになるには、倒れた人を見たときに、まず心停止かもしれないと思える教育が必要だと思います。
小川氏:我々医師も、普段から周りにいる人の様子を見て、発作を起こした人を早く見つけられるよう心がけています。できれば、一般の人も同様のことができるようになる教育が必要だと思います。
最後に、第1回、第2回のメディアワークショップで座長をお務めになった日本心臓財団理事の山口徹先生にご挨拶を頂戴いたします。

日本心臓財団理事、国家公務員共済組合連合会虎の門病院院長:山口徹氏