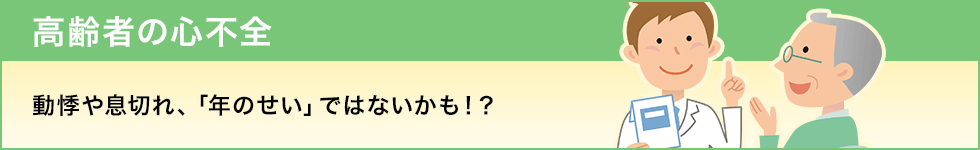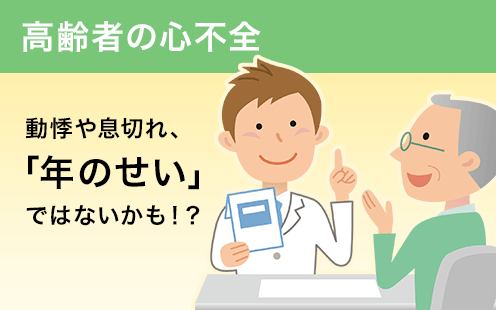耳寄りな心臓の話(第9話)『心臓に手をつける奴は』
『心臓に手をつける奴は』
−T・ビルロート、1881年−
川田志明(慶応義塾大学名誉教授、山中湖クリニック理事長)
心臓は体の中心にあって、昔から冒すべからざる神聖な場所と考えられてきました。このため、心臓が病魔に襲われても仕方がないと諦め、医療の中でも長く手付かずのままでした。このように、胸壁のすぐ下の僅か数センチしか離れていない心臓に外科医がなんとか到達できたのは、ほんの百年前のことであり、わが国でも人工心肺を用いて開心術が行われるようになってからは未だ50年ほどしか経っていません。
『病、膏肓に入る』
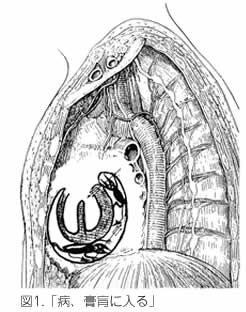 古代エジプトでは、心臓は中枢的な器官であり、理性も心臓の中にあり、愛とか勇気とかの感情を起こさせる臓器と考え、再生を願ってミイラにするにも心臓は取り出しませんでした。紀元前4世紀ころの古代ギリシャ最大の哲学者とされるアリストテレスは、「神の宿る心臓だけは、傷をつけてはいけない」といっていますし、医聖とされるヒポクラテスでさえも「心臓の傷は致命的で治療の対象にならない」と指摘しています。
古代エジプトでは、心臓は中枢的な器官であり、理性も心臓の中にあり、愛とか勇気とかの感情を起こさせる臓器と考え、再生を願ってミイラにするにも心臓は取り出しませんでした。紀元前4世紀ころの古代ギリシャ最大の哲学者とされるアリストテレスは、「神の宿る心臓だけは、傷をつけてはいけない」といっていますし、医聖とされるヒポクラテスでさえも「心臓の傷は致命的で治療の対象にならない」と指摘しています。
やはり同時代の中国の注釈書「春秋左氏伝」に『病、膏肓(こうこう)に入る』という話があり、病にかかった王の夢枕に立った病魔の二人が、「隣国から名医が来るというから、お前は膏の下に隠れろ、俺は肓の上に隠れる」といい、王を診察した名医が「病は膏の下、肓の上に入ったので既に施しようがありません」と匙を投げたという。一般には、道楽や趣味などに夢中になって、もうどうにもならなくなるという意味で用いられますが、もともとは膏肓と呼ばれる胸骨の下、横隔膜の上の隙間に病魔が入ると討ち取るのが難しいという話で、今で言うと心膜炎や胸膜炎、あるいは狭心症や心筋梗塞にかかると重篤で手が付けられないと言わせているようです(図1)。
拍動する心臓の縫合
 医学が飛躍的に発展した19世紀末に、外科の泰斗とされたウイーン大学のテオドール=ビルロートが初めて胃切除術に成功します。彼の実施したビルロート?法、?法は現在でも標準的な術式として胃癌の手術などに用いられています(図2上段、胃切除術)。
医学が飛躍的に発展した19世紀末に、外科の泰斗とされたウイーン大学のテオドール=ビルロートが初めて胃切除術に成功します。彼の実施したビルロート?法、?法は現在でも標準的な術式として胃癌の手術などに用いられています(図2上段、胃切除術)。
職人芸の外科から科学的な外科、理論外科へと進化させたのもビルロートでしたが、その彼でさえも神聖な心臓に手を付けるなどは大変な暴挙と考え、「心臓を縫合しようとする外科医は、我々の仲間でない」と発言したことで、心臓外科の開始が50年も遅れたともいわれています。
この逆境にありながら、1896年になってウイーンに近いフランクフルトのL・レーンがナイフによる右室刺創を受けた青年の心臓縫合に成功したのが世界初の快挙で、今日の心臓外科の幕開けとなりました。ビルロートが没した翌々年のことでした。
その6年後の1902年にはアメリカのアラバマのL・ヒルが13歳男児の右室刺創の縫合に成功し、この頃ボストンのある外科医は、『胸壁から心臓までは僅か2、3センチの距離なのに、ここに到達するまで2,000年以上もかかった』と述懐しています。
このような経緯をたどって、1950年代初頭の米国に次いでわが国でも人工心肺を用いた開心術が始められました。
知音のトリオの殿堂
かつてウイーン大学病院中庭にあるビルロートの立像を訪ねたことがあります。丁度ウイーンの街は「音楽月間」ということで数々の催し物があり、それではとウイーン楽友会ホールの「黄金の間」でロンドン・ロイヤルフィルによる演奏を堪能し、旧知のジョン博士夫妻が待つレストランへ急ぎました。
外科の巨匠ビルロートの銅像にめぐり逢え、ブラームスの交響曲第三番もアシュケナージの指揮ですばらしかったなどと話した途端、目を丸くした夫妻から"ビルロートとブラームスの一会(いちえ)"と言いながら握手を求められたが、こちらには皆目見当が付きません。
なんでも、ビルロートはチューリッヒ時代には自宅で定期的に弦楽四重奏のコンサートを開き、自らも第一バイオリンを担当し、新聞にも音楽評論を寄稿するほどの楽才があり、ヨハネス=ブラームスとの交流もあり早くから知音(ちいん)の友になったといいます(図2下段)。
外科医ビルロートはまた弟子たちに、医者は医学とともに歴史や文学などにも幅広く素養を広げ人間性の滋養に努めるべきと説きました。ヨーロッパ随一の外科医として引く手数多(あまた)の中、ブラームスと一緒ならとチューリッヒから音楽の都のウイーン大学に赴任した経緯があります。ブラームスによる弦楽四重奏曲の作曲にもビルロートからの助言が多々あったようで、第一番、第二番はビルロートに献呈されたものとのことでした。
青きドナウで迎える新年
また、音楽の殿堂であるウイーン楽友会ホールの柿落(こか れお)としには楽友会長のブラームスが指揮をとったことなども聞かされ、さすが音楽の本場の人の知識は凄いと感心するとともに、今日一日の出来事が又とない一期一会に思えてきました。
れお)としには楽友会長のブラームスが指揮をとったことなども聞かされ、さすが音楽の本場の人の知識は凄いと感心するとともに、今日一日の出来事が又とない一期一会に思えてきました。
ブラームスはまた、「青きドナウ」や「ウイーンの森の物語」など作風の異なるヨハン=シュトラウス2世の音楽にも魅せられ、ビルロートらとともにウイーンの郊外で語り明かすことも多かったようです(図3)。
音楽の都ウイーンの新年は「青きドナウ」の演奏とともに明けるといわれ、ウイーン楽友会ホールの「黄金の間」で行われるニューイヤー・コンサートは世界に放映されています(図4)。
前年に朋友ビルロートを失った傷心のブラームスは、シュトラウスのオペレッタ『理性の女神』の初演に、黄胆が出ていたにもかかわらず出かけ、翌月に肝癌のために亡くなりました。音楽の都ウイーンを舞台に活躍したテオド−ル、ヨハネス、ヨハンの知音のトリオは、音楽で結ばれた偉大なる文化人として、ウイーン市中央墓地に眠っています。

大河ドナウの船旅
初めてウイーンを訪れた時は生憎の雨で、プラター公園に向かう橋から眺めたドナウは流れが早く濁っていて、あこがれの青きドナウには対面できませんでした。二度目の時も前日が大雨だったとかで目的を果たせず、ブダペスト経由ウイーンへの旅では三度目の正直とドナウの船旅と決めました。
快晴に恵まれ今度こそはと期待したのですが、4時間もかけたウイーンまでの船旅でも、水の澄んだ青きドナウとの対面は叶いませんでした。それでも川べりに建つ古城や砦がロマンチックに映り、旅情を和らげてくれました。
ドイツ南西部に源を発するドナウ川は約2800キロ流れて黒海に注ぐ大河ですが、流出土も多く水が澄むことはないようです。しかし、ウイーンの森から見下ろすドナウは晴れ上がった紺碧の空の青さが川面に映り、森の緑とマッチして昔も今も変わらず美しいのだと。
清流に冨んだ日本の河川では青く澄んだ水は珍しくもありませんが、ヨーロッパの大河では望みようもなく、結局は青は澄み渡った空の色であり、これを映す水面の色でもあったわけです。
『美しく青きドナウ』は国破れて落ち込んだ国民を鼓舞する曲をワルツ王・シュトラウス?世に依頼されたもので、原題は"An der schoenen blauen Donau"となっています。直訳しますと『美しく青きドナウの水面に』となりますが、『美しく青きドナウ』として広まったために、多くの日本人はドナウ川の水は青く澄んでいるのだと異国の大河に思いを馳せてきたようです。