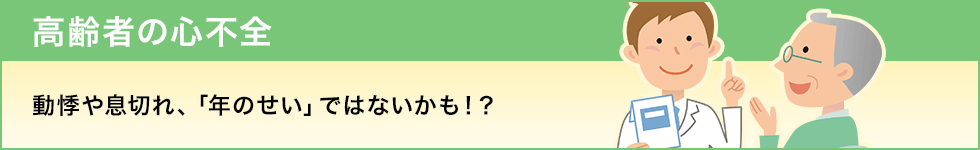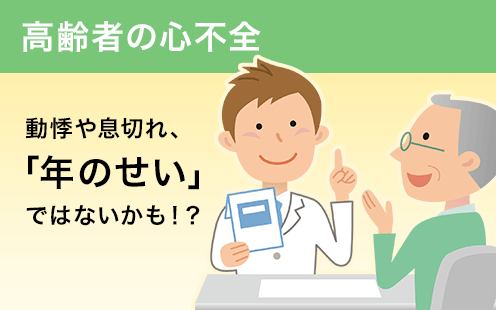耳寄りな心臓の話(第8話)『柳から生まれたアスピリン』
『柳から生まれたアスピリン』
−フェリックス・ホフマン 1897年−
川田志明(慶応義塾大学名誉教授、山中湖クリニック理事長)
今日でも解熱鎮痛剤の王座を占めるアスピリンは柳の樹皮から抽出したサリチル酸をヒントに合成された白色無臭の薬剤ですが、1世紀にわたって熱と痛みの薬として世界中で服用されています。
三十三間堂の楊枝法要
日本でも、かつて「柳で作った楊枝(ようじ)を使うと歯が うずかない」という伝承があり、柳の樹皮や葉に、鎮痛や抗炎症作用のあることが知られていました。因みに、歯の間に挟まったものを取り除くのに用いる爪(つま)楊枝・楊子などはもともと楊柳とも呼ばれる柳の枝から作ったことからの名称です。
うずかない」という伝承があり、柳の樹皮や葉に、鎮痛や抗炎症作用のあることが知られていました。因みに、歯の間に挟まったものを取り除くのに用いる爪(つま)楊枝・楊子などはもともと楊柳とも呼ばれる柳の枝から作ったことからの名称です。
三重県の紀和町に楊枝薬師堂があり頭痛山平癒寺とも呼ばれていますが、ここを霊地として京都に建立された三十三間堂でも「楊枝浄水加持会」といわゆる「やなぎのお加持」が行われています。楊枝(柳の枝)をさした浄水を信徒の頭上に注ぎ、頭痛寛解とともに無病息災・悪病除去を願うもので、お寺で手渡される頭痛お守りにも柳が入っているようです(図1)。
由来としては、仁安2(1167)年、後白河法皇が頭痛で再々苦しまれて祈願したところ、薬師如来が現れて「熊野川のほとりの柳の大樹で都に大伽藍を建立し、かつ我が像を彫刻して奉れば、頭痛たちどころに癒えよう」とお告げがあり、柳の大木を棟木として三十三間堂を建立し像を奉ったところ法皇の頭痛が平癒したもので、法皇自らが大導師となって開眼法要を行い、以後頭痛山平癒寺と号されたといいます。
内陣の柱間が33間あるので三十三間堂として知られ、西側の縁から北端までの66間を射通す通し矢の競技でも有名ですが、堂内にある一千一体の千手観音はあまねく衆生を救済し、その四十二手の中の一本に楊柳手があって、とくに頭痛や病を除く功徳があるとされています。
バイエルのアスピリン
すでに古代ギリシャ・ローマの時代から、葉の裏が白い柳の樹皮に解熱作用のあることは知られていました。例えば紀元前のギリシャのガレンやヒポクラテスが柳の皮に鎮痛作用のあることを述べています。
 その後も柳の樹皮は種々の痛み止めに用いられてきましたが、1826年になって柳から有効成分が分離されラテン語の柳がsalixサリックスであることからsalicinサリシンと命名されました。1853年にはフランスの化学者がアセチルサリチル酸の合成に成功したのですが、薬として世に出す努力をしないままに埋もれてしまいました。
その後も柳の樹皮は種々の痛み止めに用いられてきましたが、1826年になって柳から有効成分が分離されラテン語の柳がsalixサリックスであることからsalicinサリシンと命名されました。1853年にはフランスの化学者がアセチルサリチル酸の合成に成功したのですが、薬として世に出す努力をしないままに埋もれてしまいました。
1897年になってドイツにあるバイエル社の化学者フェリックス・ホフマンはサリチル酸をアセチル化することでアセチルサリチル酸、のちのアスピリン(Aspirin)を生成することに成功して脚光を浴びました(図23)。
バイエル社は「アスピリン」の特許権を取得して、1899年には薬として発売を開始して大量生産に入り、解熱鎮痛剤、リュウマチの薬として世界中で用いられるようになりました。
「アスピリン」の特許権の切れた後の後発医薬品が出回りましたが、1935年当時でオリジナルのバイエル社の「アスピリン」は1錠91ペニヒ(1/100マルク)だったのに、他社のは約1/3の32ペニヒだったという記録が残されています。医薬品の販売に厳しい米国でもアスピリンだけは別格で、早くから処方箋なしでドラッグストアなどで購入できる大衆薬の一つでした。
 今日では、サリチル酸系薬剤としてアスピリン、サリチゾンのほかダイアルミネート配合のバファリン(81?、330?)、サルソニン、カシワドール、カンボリジンなどがあります。特許権の切れた段階でゾロゾロ出ることから「ゾロ薬品」あるいは「ジェネリック薬」と呼ばれる後発医薬品は、ブランド品をもとに開発生産されるので研究開発費がかからず、価格も何分の一かに抑えられるのですが、「安かろう、悪かろう」のイメージがなかなか拭えないようです。
今日では、サリチル酸系薬剤としてアスピリン、サリチゾンのほかダイアルミネート配合のバファリン(81?、330?)、サルソニン、カシワドール、カンボリジンなどがあります。特許権の切れた段階でゾロゾロ出ることから「ゾロ薬品」あるいは「ジェネリック薬」と呼ばれる後発医薬品は、ブランド品をもとに開発生産されるので研究開発費がかからず、価格も何分の一かに抑えられるのですが、「安かろう、悪かろう」のイメージがなかなか拭えないようです。
ほかにも、サリチル酸をエステル化することでサリチル酸メチルが生成され、サロンパスやサロメチールなどの外科用湿布薬が登場しました。さらに、サリチル酸誘導体のパラアミノサリチル酸はパス(PAS)と呼ばれる結核薬として用いられています(図3)。
心筋梗塞・脳梗塞の予防に
世界中で解熱鎮痛に「アスピリン」を多用するようになって、幾つかの問題が起こりました。カリフォルニアの開業医クラベンは扁桃腺摘出や抜歯を数多く手掛けてきましたが、痛み止めにアスピリンを用いるようになってから、手術後の出血の多いことに気付くとともに、毎日一回はアスピリン・ガムを口にしたことのある400人の中には2年間で一人も心筋梗塞にかからなかったことに注目しました。
その後、アスピリンの抗血小板凝集作用のあることが証明され、心筋梗塞や脳梗塞の予防に用いられるようになり、服用量もクラベンが最初に用いた325?よりもずっと少く、1/4の81?が適量と考えられるに至り、現在では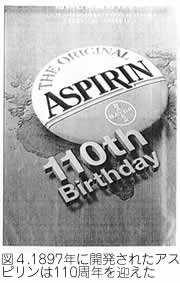 錠剤も81?のものが普及しています。
錠剤も81?のものが普及しています。
一方で、水痘(水ぼうそう)やインフルエンザなどのウイルス感染にかかっている小児が回復期に激しい嘔吐、痙攣を起こして意識不明となり、肝臓障害が急激に出現して重体に陥るライ症候群と呼ばれる病態がありますが、患児にアスピリンなどピリン系の薬物を使用した時に多く見られることから、これらの薬剤との関連が疑われています。イギリスなどでは原則として、12歳以下の小児にはアスピリンを使わないことになっています。
1960年頃までの解熱剤にはアミノピリンやスルピリンなどピリン系と呼ばれるものが多く用いられ、アソピル入りの風邪薬を飲んだ後のショック死が社会問題になったことがありました。ただし、「アスピリン」は作用もほぼ同じでピリンという字もついていますが、「ピリン系」ではありません。
アスピリンは開発されてから110年が経過しましたが、この薬ほど全世界で用いられ、家庭薬としても浸透し重宝されている薬の例はほかに見当たりません(図4)。
「アスピリン」はアセチルサリチル酸を製剤したバイエル社の商品名ですが、薬といえばほとんどが薬草や生薬が主だった時代に世界で初めて合成された薬剤であり、現在でも多く用いられている歴史的な薬であることから、あえて商品名を用いました。