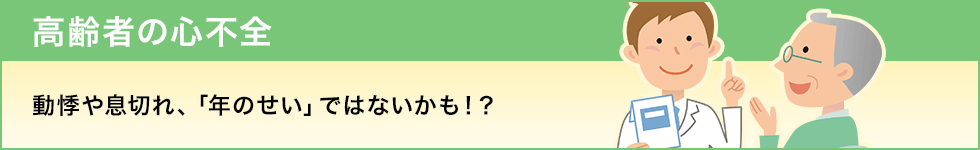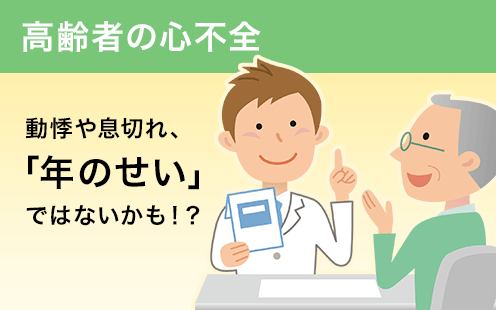ドクターのつぶやき-千の風になって篇-
 患者さんの訃報
患者さんの訃報
療養型の病院に移っていった患者さんの奥さんからお手紙をいただいた。ご主人の訃を知らせるものであった。暖かい看護の中で、安らかな最期であったと書かれてあった。脳梗塞を起こして後、長い年月の間に、肺炎を繰り返しながら、次第に衰弱していかれたのであった。享年80歳であった。人生には必ず終わりがある。しかし、すべてに満足して、やすらかに終焉を迎えるケースは多くはない。すこしばかりの行き違いが大きなシコリとなって、後悔を残すことがあるものである。ひたむきに懸命であった奥さんの表情を思い出しながら、紹介先の病院で納得のいく看護をうけ、思い残すことがない様子であることを心から嬉しく思った。(未掲載)
千の風になって
人生の終わりに近づくと、ときに自分の死後の姿を考えることがある。通常は、亡骸は骨壺の灰となって、墓地に納骨される。最近は、献体について、相談を受けることもある。献体登録をしている私の場合、私は文字通り、墓地にはいない。「千の風」になって、何かのはずみにふと思い出してくれる人があったとき、その瞬間に私はそこにいるというような存在になるのであろう、と思っていた。
そんな矢先の先日、ある人から、「千の風」は般若心経の思想ではないかと教えられた。「色即是空」の空が風だという。「千の風」が仏教に通じるとは思っていなかったので、驚いた。新井満氏の「千の風」に付された解説を見直すと、死者が「風に生まれ変わる」とお考えのようであった。転生の思想があったことに、またまた、驚いた。般若心経は一枚足らずの短い経典であるが、解説書には膨大な、そして、実にさまざまのものがある。諸行無常の教えとするものから、「この世とあの世の間で永遠の旅をつづける」という解釈もある。しかも、新井満氏には自由訳般若心経という著書があった。そして、そこには、「古いいのちは新しいいのちとなって生まれ変わる」と解説してあった。
般若心経は6世紀ころに書かれたものの翻訳であるが、今の形になったのは1世紀ころらしい。生きている人に死の迎え方を説く教本である。「千の風」はいつできたか判らない短い詩であり、残された人に宛てた死者からのメッセージである。死とは実に古い時代からの大きなテーマだった。自分の死後の扱いを考えていて、別々のものと思っていたこの二つに共通した思想が考えられることを知って驚いた。しかし、自分の場合は生まれ変わろうとは思わない。自分にとって、死は消滅を意味する。消滅した後にも、ときに思い出してもらうことがあれば嬉しい。自分はやはり、冒頭に記したような自分なりに解釈した「千の風」になりたいと思った。(2007年11月号掲載)
献体
魯迅が日本にきたのは、明治35年、1902年である。同じ船には数人の中国人留学生が乗っていた。魯迅は仙台に行ったが、同行者の一人は金沢の医学専門学校に留学した。4年後、この人は帰国して、母国に中国人による学校と病院を創設した。金沢大学の卒業生名簿にこの人の名を発見し、子孫を辿って、その生涯を調べたある先輩がこのことを医学雑誌のエッセイ欄に書いていた。そこには、当時、この人にとって、北陸の地に「深く残った思い出は解剖実習」であり、「屍を探りながら、血管や臓器を歴然と目にしたとき」の感激であったと書かれてあった。今日、このような学生の解剖実習に供される屍は民間有志から大学に登録される献体にもとづいている。
実は、私は死後の私自身を学生実習に提供するべく、北陸の大学に献体登録をしている。30年前のことであった。この登録をしたことで、生涯を終えた後、私の遺体は大学に引き取られ、1?2年後に、他の方々と一緒に焼却されて、大学の慰霊碑に納骨される。解剖実習は医学生が医の道を歩むことになったとはじめて実感する瞬間である。昔、魯迅たちの一行が留学してきたとき、もっとも印象に残ったのが、解剖実習であったというこの記事は、そのときの対象となった遺体のように、私自身もこれから医学生たらんとするものに、大きな感激を与えるであろうという誇りと、それが、この人たちがさらに、よき医療者になるための気概をもつことにも繋がっていってほしいという期待をもたせるものであった。(2008年2月号for media掲載)